コダモンです。(@kodamon)
日本の職場では先輩後輩の関係が重要視されます。
「同年代でも在籍期間が長い方が先輩?」
「年上でも中途入社だったら社歴が長い方が先輩?」
そのような事を気にしながら働く必要がある。

正直めんどう
日本の『先輩・後輩』という文化は欧米諸国にはほとんどありません。
海外の企業にもそのような風潮はなく、基本的には上司・部下の役職関係による上下しかない。
まだ『社歴』とか『どちらが先輩か』とか気にして働いてるの?
年功序列の日本企業

日本企業の多くは年功序列の制度で成り立っています。
賃金や退職金が年功重視なので、給料は段階的に昇給の恩恵を受ける事ができるし定年まで勤めきれば退職金もたんまりもらえる。

いわゆるエスカレーター式
年功序列というのは終身雇用を前提とした制度です。
ざっくり言えば、会社側が「倒産しなければ定年まで面倒見てあげるよ!」と社員に保証する制度。
退職金の額も勤続年数に応じて増える仕組みです。
(厚生労働省, 令和3年退職金年金及び定年制事情調査, 2022年2月時点)
そのため、日本で会社員をする場合は基本的に同じ会社に長く勤めることが良しとされます。
新卒で入社した会社で役職定年を迎えることが『理想』とされてきたわけです。
このように定年まで同じ会社で働くという終身雇用の制度が日本企業に根付いているため、年功序列が日本の働き方のベースを担っているわけですね。
しかし…。
この制度のもとに成り立つ組織で実際に働いてみると、デメリットも見えてきます。
年功序列のデメリット

年功序列という制度はあくまで『会社を辞めないこと』を前提として成り立ちます。
そのため…。
仕事や職場が合わなくても「とりあえず我慢をする」という人が大勢出てきます。
退職金をがっぽりゲットしたければ、会社がどんなに嫌でも息長く勤める必要があるということ。
人間関係の摩擦や長時間労働がどれほど苦痛でも…とにかくひたすら耐え抜いて頑張る。
そのような根性論的な働き方がデフォルトになるケースが多いです。

若いうちは特に大変
こういった年功序列制度の根幹には、次のような考えがあります:
要するに、基本的には社歴が長い人や年齢が高い人が重宝されるということ。
確かに、敏腕ベテラン社員が上手にリーダシップを発揮してくれるのであれば、誰もそれに対して異論はないでしょう。

デキる人なら良い
社歴が長い先輩社員が頼りになる人であれば、自然と尊敬の念も生まれます。
でも…
現実はちょっと違う。
ただ単に勤続年数が長いだけで会社のお荷物になっている人もいるし、社歴が長いだけで「自分は偉い!」と勘違いして横柄な態度を取る人もいます。
最近は『老害』なんて言葉もよく耳にしますが、まさにソレ。
「どっちが先輩?」「社歴が長いから敬語を使うべき?」とかいちいち気にして働くのは、各々の勝手です。
しかし、それは組織における上下関係とは別物!だということです。

別に年上が偉いわけじゃない
「先輩・後輩は日本の文化だ!」
「先輩を敬うのは当たり前だ!」
そのように言う人もいるけれど、それって実際に仕事をする上で誰に何の恩恵があるの…?
「どちらが先輩か」などと気にして働いてもメリットなんか一つもないと感じるのは、わたくしコダモンだけでしょうか。
社歴や入社年度を気にするダサい社会人
日本人はそもそも相手の年齢を気にしがち。
初対面でも「ちなみに今おいくつですかー?」などとデリケートな質問を急に放り込んで来る人もいる。

海外だったら失礼なヤツ
日本には『目上の人には敬語を使う』などの礼儀やマナーがあるので、相手に失礼のないように振る舞う必要がある。そのため、あくまで相互確認のために相手の年齢を聞く場合があります。
また、日本人は義務教育の過程で先輩・後輩の意識を学校で植え付けられるので、大人になっても「どちらが先輩?」などと気にする人が多いのもまた事実。

その気持ちはわかる
国民性もあるだろうし、相手によっては上下関係に厳しい人もいるので、むやみに地雷を踏まないために年齢やら社歴やらを確認したくなるわけですね。
まぁ、それはそれで別にいいのだけれど…。
これには問題もあります。
例えば、相手が自分より年下だと判明した途端に露骨に態度を変える人。
社歴の長さや入社年度でマウントを取ろうとする人が出てくるのです。

あれ本当に迷惑
途中まで敬語で話していたのに、相手の年齢を知った途端に「えっ!君年下だったの!?」と言って露骨にタメ口に切り替わる人とか。
同じ平社員同士なのに、『年齢が上』『社歴が上』という理由で急に上から目線になる人とか。
いやいや…。
どっちが先輩かなんてマジでどうでもいい。
そんな事をいちいち気にして働いても、余計なストレスが増えるだけ。

疲れるだけ。めんどい
確かに、職場では『指導する側』と『される側』といった師弟関係が発生する場合があります。
でも、それはあくまでも業務遂行上の関係なわけで…。
社会人になっても年齢や社歴でマウントを取りたがる人は正直ダサいです。
パワハラまがいの上下関係って誰得なの?

話を海外に移します。
海外の企業で勤めていると年下の上司が普通にいます。
社歴10数年のベテラン社員が、ぽっと出の若造の部下になる事もある。

マジである
今現在とあるドイツ企業に勤めていますが、30代で既に『部長クラス』のポジションに就いている優秀な若いドイツ人がいます。
当然、そのような人材の下には年上の部下が何人もいるわけです。
そういった職場環境は欧米諸国にはよくある事で、成果主義の世界の中で本当にデキる人のみが上へ行ける仕組みになっています。
国が変われば文化と習慣も変わるため一概には言えませんが、欧米諸国の企業風土の特徴の一つとして『フラットな人間関係』があります。日本では何かと年齢やキャリアで上下関係を決めようとしますが、例えばドイツにそのような風潮はありません。親しい上司とは下の名前で呼び合い、お互い”タメ口”で会話をします。
日本と海外を比較しても、ぶっちゃっけあんまり仕方ない。
けれど、日本とドイツで実際にサラリーマンをしてみた自分としてはドイツの方がサッパリしていて断然働きやすいです。
仮に相手の役職が上だったら敬語を使えばいいし。
それ以外の上下関係はフラットな関係性でいいんじゃないの?
「自分の方が年上だ!」
「自分の方が入社年度が先だ!」
そうやってマウントを取ろうとする人もいるけれど、別にその人が偉いわけじゃない。

上司ですらない
「年上だから」
「先輩だから」
「社歴が長いから」
そのような理由で傲慢な態度を取る人は、周りから尊敬されない。
職場ではめんどうな人というレッテルを(本人の知らない所で)貼られることでしょう。
ちなみに、わたくしコダモンが以前勤めていた日系大手企業の営業部はバリバリの体育会系でした。
そして、そのような職場は未だに多くの会社に残っている。
(厚生労働省,職場のパワーハラスメントに関する実態調査,2020年12月時点)
「年齢が上!」「社歴が長い!」というだけで社会的地位が強いと勘違いしている人は、そのほとんどがパワハラ予備軍です。
「先輩からの誘いは断らない!」
「先輩より早く帰らない!」
パワハラまがいの上下関係は時代遅れもはなはだしいです。
『先輩後輩』はなくならない?

以前勤めていた大手日系企業では、新入りがパシリや雑用を任されていました。
職場の人間関係もガッチガチの縦社会。まさに体育会系のノリです。
そのため、入社したての当時は業務以外の余計なストレスがハンパじゃなかったです。
日本で実際に社会人をやってみて、通算10年以上日本とドイツでサラリーマンをしてみて、思う事があります。
それは…。
日本の先輩後輩は今後もなくならないという事。
日本の会社では先輩社員が若手の指導者になる事が多く、お互い平社員同士であっても自然と上下関係が生まれるよう”仕組み化”されています。

入社順に決まる
日本は伝統を重んじる国であると同時に、良くも悪くも大きな変化を嫌う傾向があります。
基本的には既存の組織体制や仕組みが大きく変わる事は好まれないので、効率や生産性は度外視で職場の慣行や昔ながらのルールが延々と受け継がれます。
その結果、時代遅れの体育会系の会社や部署がいまだに存在する。
そして、どの職場にも社歴とか入社年度で態度を変える人が必ず一人や二人はいる。

なかなか変わらない
そういった意味では、日本企業で働く場合に先輩後輩の関係性から抜け出すことはほぼ不可能でしょう。
しかし、それはあくまでも礼儀やマナーといった観点からの話。
年齢や社歴による人間関係の上下に対する意識は今後の日本では薄れていくかもしれません。
人間関係の上下を年齢で決めない!

昨今の日本では外国人労働者の受け入れをはじめ多様な価値観による変化が浸透しつつあります。
同時に、柔軟な思考を持った若い世代やネット世代が新しい風を吹かせている。
「仕事が終わったら帰ります」
「休みたい時に休みます」
そのように、労働者の権利を真っ向からぶつけて職場の空気を読まない人もちらほら出て来ました。

良い意味で空気を読まない
一昔前ならば、そのような社員は「生意気だ!」「勝手な事するな!」などと一喝されていたことでしょう。
「先輩がまだ働いてるんだから残業しろ!」
「周りが休まないのに1人だけ休むやつがいるか!」
このような反応は、今のご時世では完全にアウト。
先輩後輩の関係性は、おそらく今後もなくならない。けれど、年齢や社歴でマウントを取ってパワハラまがいの指導をするという事に対して世間の風当たりが強くなっています。

働き方はどんどん変わる
日本企業にありがちな『付き合い残業』や『半ば強制の飲み会』などは、先輩の命令は絶対!といった体育会系のノリのおかげで成立していました。
しかし、そのような理不尽はこのご時世もう通用しない。
将来の日本を担う若い世代の台頭により、根性論や精神論で社員を働かせる職場はいつか淘汰されるでしょう。
会社での先輩後輩や上下関係に対する意識も、時代と共に変わるかもしれない。
「同年代でも在籍期間が長い方が先輩?」
「年上でも中途入社だったら社歴が長い方が先輩?」
そういった無意味な議論もいつか無くなる日が来る事を祈るのみ。

期待しよう
人間関係の上下に固執しても生産性は上がらないし、スムーズなコミュニケーションのためには余計な壁が無い方がいい。
『社歴』とか『どちらが先輩か』とか気にして働いても、何の意味もないのです。
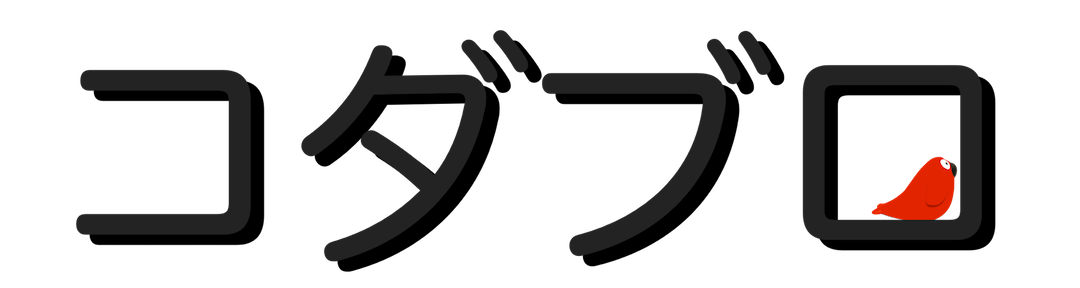



コメント
今まさにそんな会社で働いています。とにかくペコペコしていないと貴重な若手でもすぐに潰しにかかってきますね(笑)
まぁ〜疲れます、他の記事も拝見しましたが
足の引っ張り合い、無駄な事の多さで現場も疲弊。ルールを作る事で逃げる状態を作る上司などなどでウンザリします。
4カ国語とは凄まじいですね。
44歳にもなって英語を勉強し始めましたが
今更勉強してどうするの?と言われました(笑)
結果はどうなるか分からんがほっといてくれと(笑)
ストレスフリーで人生満喫して下さい!
貴重なお話ありがとうございました。
コメントありがとうございます。
それは…お疲れ様です。
英語を勉強し始めたというのは共感しか持てません。年齢はまったく関係ないですね!
周りの人達とは違う価値観、違う文化圏の人達と交流の機会を増やしてくれる、世界観を大いに広げてくれるのが『語学』だと思っています。
応援しています。